「不登校の子どもが閉じこもってずっとゲームをしている。これって、依存? とめるべき?」
「子どもがスマホを欲しがっているけれど、スマホ依存にならないかが心配」
「思春期の子ども。過度なダイエットや自傷行為をとめたい」
「学校で傷ついている子にどんなふうに接したらよいのか知りたい」
この講座では、子どもの「心の傷」について発信を続けている精神科医の松本俊彦さんに、「依存」をテーマにお話を伺います。
子どもたちのゲーム、ネット、ダイエットへの依存行為やリストカット、オーバードーズなどに接すると、周りの大人の多くはたじろぎ、戸惑います。
松本先生は、望ましくないものを取り上げるだけでは、「依存」の解決にはならず、真の回復にはつながらないと話されています。
・そもそも依存とは?
・子どもの心の傷と依存の関係、メカニズム
・「回復」への道
・周りの大人の受けとめ方、持っておきたい知識
講座では、皆さんの疑問に添いながらわかりやすくお話ししていただきます。
心配事がある方、ぜひ事前に質問をお寄せください。
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センター、フリースクールスタッフの方にもおすすめです。
一緒に、子どもたちの育ちの支えていきましょう。
▼こんな方におすすめです
・行き渋り、五月雨登校、不登校状態の子どもを持つ保護者
・依存、オーバードーズ、リストカット等の自傷行為についての知識を深めたい方
・フリースクール、オルタナティブスクールの運営者、スタッフの方
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センター、学校教諭の方
▼こんなことが得られます
・今、辛さを感じている子どもへの眼差し、関わり方
・心配な子どもの将来の見通し
・「依存」についての基礎知識
◆講座開催日:2024年10月8日
※登壇者の肩書は開催当時のものです。
【2024年度赤い羽根福祉基金助成事業】
登壇者/モデレーター
-

松本 俊彦
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部 部長
1993年佐賀医科大学卒業。国立横浜病院精神科、神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科、国立精神・神経センター精神保健研究所司法精神医学研究部室長、同研究所薬物依存研究部室長、自殺予防総合対策センター副センターなどを経て、2015年より現職。2017年より国立精神・神経医療研究センター病院薬物依存症センター長兼務。
著書に『世界一やさしい依存症入門; やめられないのは誰かのせい? (14歳の世渡り術)』(河出書房新社)等がある。 -

前北 海
NPO法人多様な学びプロジェクト副代表理事
フリースクールコンサルタント


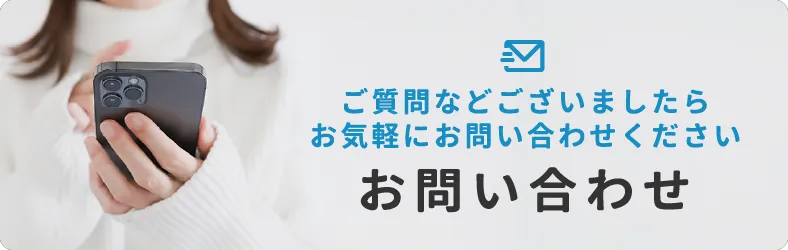

コメントを投稿するには、ログインが必要です。
ログイン